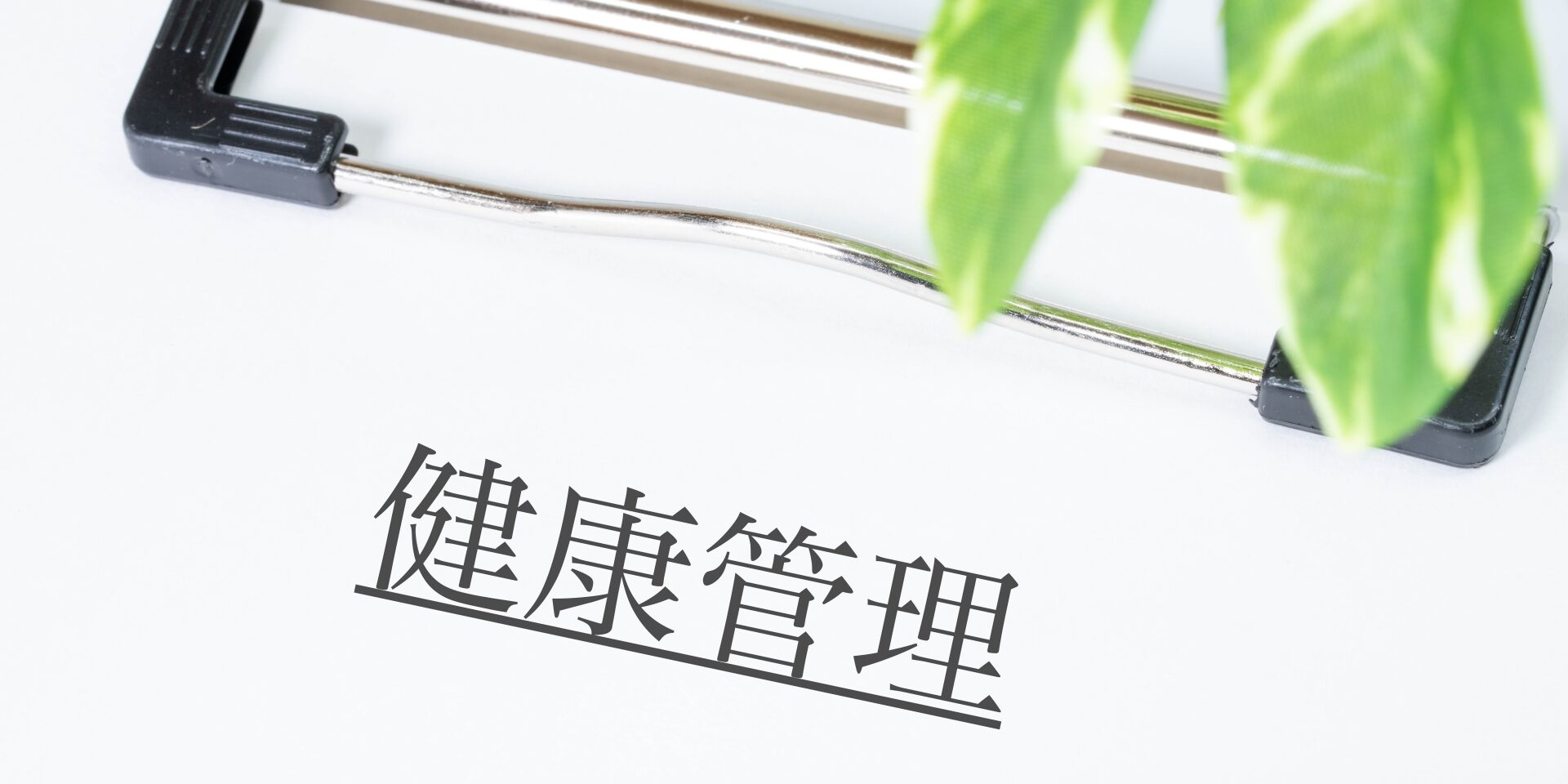ロナ禍を経て、多くの人が「心」と「体」の両面で健康の大切さを実感したのではないでしょうか。社会人として仕事を続けていくうえで、健康管理は単なる自己管理の一環ではなく、仕事の質にも直結する重要な「業務の一部」と言っても過言ではありません。
健康状態が不安定なまま働き続けると、生産性が落ちるだけでなく、重大な体調不良に発展する恐れもあります。そこで今回は、仕事のパフォーマンス向上に直結する「健康管理のポイント」を、心身両面から詳しくご紹介します。
仕事と健康は切っても切れない関係

どんなに高いスキルや豊富な経験があっても、心や体の調子が整っていなければ、仕事で本来の力を発揮することはできません。特にコロナ禍を経て、心身の健康と仕事のパフォーマンスが密接に結びついていることを実感した方も多いのではないでしょうか。
健康な状態は、仕事の効率や成果に良い影響をもたらす一方で、不調を抱えたまま働き続けると、生産性の低下や人間関係の悪化、さらには深刻な疾患につながる可能性もあります。
ここでは、健康な状態で働くことで得られるメリットと、不健康な状態で働くことのリスクについて、具体的に見ていきましょう。
健康な状態で働くメリット
1. 集中力・判断力の維持
心身が健康であれば、脳の働きも安定し、情報の処理能力や判断の正確さが保たれます。業務中に集中力が切れにくくなり、タスクを効率よくこなすことができます。
2. ミスの予防3. 前向きな気持ちで仕事に取り組める
体調が整っていると注意力が高まり、小さなミスや確認漏れを防げます。特に事務作業や医療・介護現場など、正確性が求められる仕事においては、健康状態がミスの有無に直結することも少なくありません。
3. 前向きな気持ちで仕事に取り組める
十分な睡眠や栄養、ストレス管理ができていると気持ちも安定し、自然と前向きな姿勢で仕事に臨めるようになります。仕事への意欲や挑戦心も高まり、成果につながりやすくなります。
4. チームへの良い影響
自分が健康で元気に働けていると、周囲との関係も良好になります。明るく前向きな雰囲気は、チームの士気を高め、職場全体のパフォーマンス向上にもつながります。
不健康な状態で働くリスク
1. 判断力・集中力の低下
体調が優れないと、脳の処理能力が落ち、仕事中に集中力が途切れやすくなります。些細な判断ミスや作業の遅延が発生し、業務効率が大きく下がってしまう恐れがあります。
2. モチベーション喪失
慢性的な疲労やストレスにより、仕事へのやる気や情熱が薄れてしまいます。「なんとなくやる気が出ない」「出勤するのがつらい」といった気持ちは、心身の不調のサインかもしれません。
3. 疾患リスクの上昇
睡眠不足や食生活の乱れ、運動不足、ストレスの蓄積などが続くと、風邪や感染症にかかりやすくなるほか、生活習慣病やメンタル疾患など、重篤な健康問題に発展する可能性があります。
4. 周囲への影響(ミス・トラブル)
体調不良により業務の質が低下すると、周囲にしわ寄せがいき、チーム全体の負担が増すことに。連携不足やトラブルの原因にもなり、職場の信頼関係や雰囲気に悪影響を与えてしまうこともあります。
心身が健康であれば、脳の働きも安定し、情報の処理能力や判断の正確さが保たれます。業務中に集中力が切れにくくなり、タスクを効率よくこなすことができます。
仕事と健康は、どちらか一方ではなく“セットで考えるべきもの”です。体調が万全でなければ、どれほど能力があっても本領を発揮できません。健康な体と心を維持することが、自分のためだけでなく、職場やチーム全体にとってもプラスになることを忘れずにいたいですね。
健康管理が仕事の質を変える!4つの具体策

【① 睡眠管理】
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針」では、日中に眠気がなければ睡眠は足りているとされますが、自分にとって最適な睡眠時間を知ることが大切です。
- 就寝30分前からスマホ・PCの使用を控える
- カフェインは15時までに
- 夕食は就寝3時間前に済ませる
【② 食事管理】
栄養バランスの整った食事は、集中力の維持や脳疲労の回復に効果的です。主食・主菜・副菜+乳製品・果物を意識した食事で、エネルギーを効率的に取り入れましょう。
目安
- 1日の摂取カロリー:2200±200kcal(成人の場合)
- 栄養バランスを意識した献立を継続
【③ 運動習慣】
「+10(プラス・テン)」という厚労省のスローガンがあるように、今より10分多く体を動かすことが健康寿命延伸に貢献します。
取り入れやすい運動習慣
- 通勤時に一駅分歩く
- オフィスでこまめにストレッチ
- ヨガやラジオ体操を5分だけでも習慣に
【④ メンタルヘルスケア】
体だけでなく心の健康も仕事のパフォーマンスを左右します。厚生労働省の調査では、約6割の労働者が強いストレスを感じているという結果も。早めに気づき、対処することが大切です。
セルフチェックの例
- 食欲不振や不眠が続いている
- 強い不安や落ち込みが続く
- 人と会いたくないと感じる
不調の兆しに気づいたら、無理せずまずは休息を。仕事の質を上げるためにも、心身のケアは最優先にすべきです。
健康経営がもたらす職場の変化

近年、企業活動において「健康経営(Health and Productivity Management)」の重要性が注目されています。これは、社員の健康を企業の「資本」ととらえ、戦略的に健康促進へ投資することで、生産性の向上や離職防止、企業イメージの向上につなげていく経営方針です。
社員一人ひとりが心身ともに健康な状態で働ける環境を整えることは、結果として業績の安定・職場の活性化・採用力強化にもつながります。
◆ 職場で取り入れたい健康経営の取り組み
1. 健康診断・予防接種の充実
社員の体調を定期的にチェックできる仕組みは、早期発見・早期治療の第一歩です。
- 年1回の定期健康診断の実施はもちろん、生活習慣病や婦人科系疾患のオプション検査補助など、幅広くカバーするとより安心。
- インフルエンザや新型コロナの予防接種も会社負担で実施することで、感染症の流行による欠勤・業務停滞を防ぐ効果があります。
2. ストレスチェックの実施
メンタル面のケアは健康経営の中でも重要な要素です。
- ストレスチェック制度は年1回以上の実施が義務づけられていますが、結果の活用がカギ。
- 高ストレス者への産業医面談や、部署ごとの職場環境の改善提案などに活かすことで、精神的な負担を減らし、職場の定着率向上にもつながります。
3. 管理職によるラインケア教育
「部下の不調にいち早く気づき、適切に対応する」ために、管理職の役割は非常に重要です。
- 健康状態の変化や勤務態度の異変に気づくには、日頃のコミュニケーションと知識の習得が必要です。
- 外部講師による研修や、eラーニングを活用したメンタルヘルス講座を導入し、ラインケアの質向上を目指しましょう。
4. リフレッシュ休暇や福利厚生の見直し
制度だけでなく「休みやすい風土」を作ることが、生産性とモチベーションを高めるカギになります。
- 有休取得を促進する仕組み(連休取得の奨励やリフレッシュ休暇制度)
- 時間単位の有給休暇、テレワーク、フレックスタイムの導入
- 健康増進支援として、スポーツジム・整体・健康食品の補助
これらの取り組みにより、社員が心身ともにリフレッシュでき、パフォーマンスを最大限に発揮しやすい職場環境が実現します。
🔎 健康経営の効果は数値にも表れる
健康経営を実践している企業では、以下のような成果が報告されています。
- 生産性の向上(集中力・効率性の向上による成果アップ)
- 医療費の削減(疾病予防・重症化防止による)
- 離職率の低下(働きやすい職場づくりにより)
- エンゲージメント向上(会社への愛着・やる気の向上)
企業が本気で健康経営に取り組むことで、「人が辞めない」「元気に働き続けられる」「生産性が高い」職場へと大きく変わっていきます。
社員の健康は「コスト」ではなく「投資」。まずはできることから一つずつ、健康経営の視点を社内に取り入れてみてはいかがでしょうか?
どれほど忙しくても、心と体が整っていなければ、本当の意味で「良い仕事」はできません。健康管理は特別なことではなく、日々の小さな積み重ねが未来の自分と働き方をつくっていきます。
「今日は少し早めに寝よう」「お昼は野菜を多めにしよう」「休憩中に軽く体を動かしてみよう」──そんな一つひとつの選択が、仕事の質や生活の充実度を大きく左右します。
Wematchでは、これからも“元気に働く”ことを応援し、心と体の両面からサポートできる情報を発信してまいります。皆さんがより健康で、自分らしく働ける毎日を送れるよう、私たちも伴走していきたいと思います。また、この機会に社内でもメンタルヘルス対策を見直し、職員全員が気持ちよく心も身体も健康で、パフォーマンスが高い仕事ができる環境つくりに、さらに力を入れていきたいと思います。
Wematchでは6000を超える全国の求人から転職者の方に合う求人をご紹介・ご提案を行っています。キャリア形成や面接内定までのサポートをさせていただきます。応募された際の会社側との条件の交渉についてもキャリアアドバイザーにお任せいただけます!弊社は世の中に多い会社と人材のミスマッチを解消し、会社と人材がベストマッチした社会の実現を目指しています。
人材にお困りの方やお悩みがある方などは、ぜひ一度Wematchへお問い合わせください。